新江ノ島水族館20周年イルカショースタジアムのリニューアル
~地域に愛されてきた水族館のその先へ~
Scroll Down
約4カ月間の改修工事を終え、2024年4月にリニューアルオープンした新江ノ島水族館のイルカショースタジアム。開業20周年の節目を迎えた同館がこれによって目指したのは、さらなる居心地の良さとリピートしたくなる空間の創出でした。そこには過去から脈々と受け継がれてきた経営理念や未来に向けた思いが込められています。具体的な取り組みなどについて、株式会社江ノ島マリンコーポレーション/株式会社新江ノ島水族館の堀一久代表取締役社長と、今回のリニューアルプロジェクトを指揮した日建設計 企画開発部門 エモーションスケープ部部長の坂本隆之、同部ダイレクターの安田啓紀に聞きました。

毎年約150万人が来場する水族館に成長
——2004年4月に「新江ノ島水族館」が開業してから20年が経ちました。堀さんはその少し前、2002年に社長に就任したわけですが、この二十数年を振り返ってみて、どのような感想をお持ちですか。
堀一久氏(以下、堀):祖父(堀久作氏)が1954年に「江の島水族館」を立ち上げ、母(堀由紀子氏)がしっかりとレールを敷いてくれたものを私が引き継ぎました。とにかく健全に発展させていくことを第一に、懸命にやってきましたね。
新江ノ島水族館としてリニューアルするにあたり、神奈川県のPFI(Private Finance Initiative)方式を導入し、株式会社江ノ島マリンコーポレーションとオリックスグループとで特別目的会社を設立しました。そこで県と30年間の事業契約を締結したわけですが、当時は30年なんて途方もない年月だと不安でした。でも、母は「30年なんてあっという間よ」と笑い飛ばしていました。20年経った今、確かにその通りで本当に早かったです。
水族館のような施設は開業直後が入場者数のピーク。そこから減衰していくのが一般的なトレンドです。ですから、最初の10年間はそれが切実な経営課題で、どのように客足の減少を止めて、平準化に持っていけるかばかりを考えていました。
10周年を迎えて施設の資本関係を見直し、創業家主導の事業に戻させてもらいました。以降は責任を持ってハンドリングできる立場に変わりましたし、自由な発想をどんどん事業に生かせるようになりました。スピード感も増して、結果もついてきました。そこからはあっという間でした。
堀一久氏(以下、堀):祖父(堀久作氏)が1954年に「江の島水族館」を立ち上げ、母(堀由紀子氏)がしっかりとレールを敷いてくれたものを私が引き継ぎました。とにかく健全に発展させていくことを第一に、懸命にやってきましたね。
新江ノ島水族館としてリニューアルするにあたり、神奈川県のPFI(Private Finance Initiative)方式を導入し、株式会社江ノ島マリンコーポレーションとオリックスグループとで特別目的会社を設立しました。そこで県と30年間の事業契約を締結したわけですが、当時は30年なんて途方もない年月だと不安でした。でも、母は「30年なんてあっという間よ」と笑い飛ばしていました。20年経った今、確かにその通りで本当に早かったです。
水族館のような施設は開業直後が入場者数のピーク。そこから減衰していくのが一般的なトレンドです。ですから、最初の10年間はそれが切実な経営課題で、どのように客足の減少を止めて、平準化に持っていけるかばかりを考えていました。
10周年を迎えて施設の資本関係を見直し、創業家主導の事業に戻させてもらいました。以降は責任を持ってハンドリングできる立場に変わりましたし、自由な発想をどんどん事業に生かせるようになりました。スピード感も増して、結果もついてきました。そこからはあっという間でした。
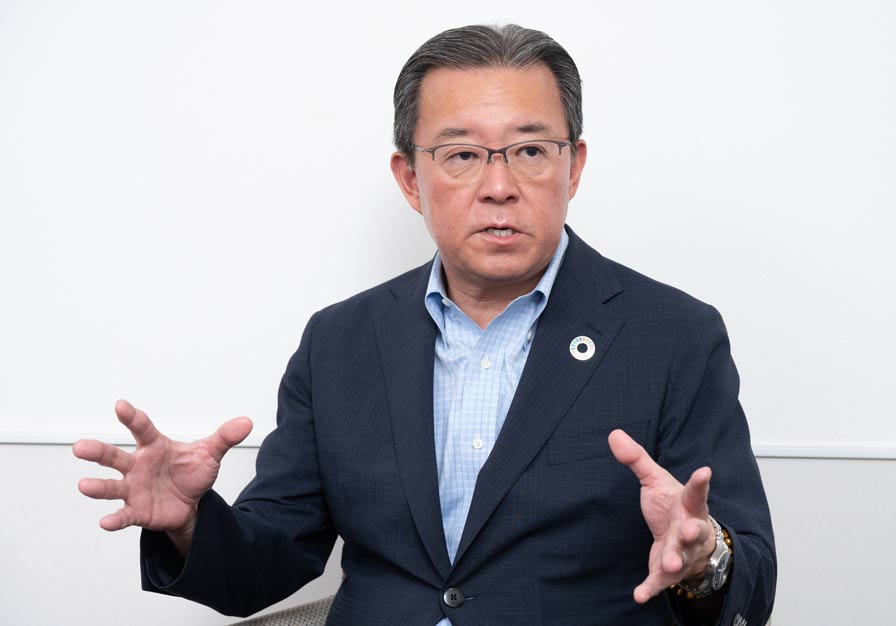
——ふたを開けてみれば、来場者数もどんどん増えて、もうまもなく累計3000万人に到達します。顧客を維持、増加させるために、どのようなことに取り組んだのですか?
堀:水族館ですから当然、生き物が主役。いかにして生き物の多様性や価値を伝えるかに注力しました。同時に、入場料をお支払いいただいて楽しんでもらう空間ですので、居心地の良さを感じてもらえるよう、ホスピタリティあふれるサービスに磨きをかけていきました。おかげさまで今では年間平均150万人ほどのお客様が足を運んでくださっています。
——江の島水族館から新江ノ島水族館へと生まれ変わる際、どのようなコンセプトを打ち出したのでしょうか?
堀:展示の大きなストーリーラインは、当時館長だった母がしたためていた思いや夢を実現させることでした。この湘南海岸に位置する水族館として、目の前に広がる相模湾から太平洋へのつながりを忠実に展示で再現して、その世界観を伝えていく点に一番こだわりました。
加えて、当館は昔から「エデュテインメント型水族館」というテーマを掲げています。これは、エデュケーションとエンターテインメントを掛け合わせた造語ですが、相模湾に生息する多数の生き物について楽しみながら学ぶ、学びながら楽しむような施設にしたいという思いも変わらずありました。
——そういったコンセプトを具現化すべく、20年前に設計者の一人として携わったのが坂本さんですよね。
坂本:水族館というのはわりと特殊な建物で、社内にも社外にも設計のノウハウを持っている人は多くありません。また、水族館ごとのポリシーや考え方がありますので、まずはそこを教わり、学ぶことに時間をかけました。
私自身は入社してまだ数年しか経っていませんでしたし、堀さんも別の業界から家業に入ったばかり。オリックスグループも水族館事業は新たなチャレンジという状況でした。すべてが手探りでしたが、皆がいい意味で既成概念にとらわれておらず、非常にエキサイティングでした。
堀:水族館ですから当然、生き物が主役。いかにして生き物の多様性や価値を伝えるかに注力しました。同時に、入場料をお支払いいただいて楽しんでもらう空間ですので、居心地の良さを感じてもらえるよう、ホスピタリティあふれるサービスに磨きをかけていきました。おかげさまで今では年間平均150万人ほどのお客様が足を運んでくださっています。
——江の島水族館から新江ノ島水族館へと生まれ変わる際、どのようなコンセプトを打ち出したのでしょうか?
堀:展示の大きなストーリーラインは、当時館長だった母がしたためていた思いや夢を実現させることでした。この湘南海岸に位置する水族館として、目の前に広がる相模湾から太平洋へのつながりを忠実に展示で再現して、その世界観を伝えていく点に一番こだわりました。
加えて、当館は昔から「エデュテインメント型水族館」というテーマを掲げています。これは、エデュケーションとエンターテインメントを掛け合わせた造語ですが、相模湾に生息する多数の生き物について楽しみながら学ぶ、学びながら楽しむような施設にしたいという思いも変わらずありました。
——そういったコンセプトを具現化すべく、20年前に設計者の一人として携わったのが坂本さんですよね。
坂本:水族館というのはわりと特殊な建物で、社内にも社外にも設計のノウハウを持っている人は多くありません。また、水族館ごとのポリシーや考え方がありますので、まずはそこを教わり、学ぶことに時間をかけました。
私自身は入社してまだ数年しか経っていませんでしたし、堀さんも別の業界から家業に入ったばかり。オリックスグループも水族館事業は新たなチャレンジという状況でした。すべてが手探りでしたが、皆がいい意味で既成概念にとらわれておらず、非常にエキサイティングでした。

当時館長だった堀さんのお母さまにもさまざまなことを教わりました。水族館は博物館の一種でありながら、劇場のようなワクワクする体験ができる場所でもあります。人々の感動を空間の中でどう実現していくのかについて、非常に造詣の深い方でした。ですから、水槽一つをとっても、「曲がった先に何がみえるか」「どうやったら水の中に没入している感覚を得られるのか」など、細かく丁寧に議論しながら進めていったことを印象深く覚えています。とにかく打ち合わせは毎日山のようにありましたが、学びながら、楽しく、もちろん緊張感もありましたが、しんどいとは感じませんでしたね。
「木を見て森を見ず」は避けたい
——今年4月に開業20周年を迎え、「イルカショースタジアム」がリニューアルしました。この経緯について教えてください。
堀:20周年の事業を考えたとき、斬新な展示スペースの増設などは物理的に難しかったため、それに代わるものとして、施設全体の美観に努めようと決めました。20年も経過すると建物の老朽化はかなり進みます。施設をしっかりと維持するための修繕コストは年々重くなっていました。中でも最も傷みの激しかったのがイルカショースタジアムでした。
他方で、我々はまた来たくなるような「居心地の良い水族館」をうたっています。20年という節目にそこを再認識したいと思いました。イルカショースタジアムはお客さまが滞在するスペースとして一番広い場所でもありましたし、本当に眺めも素晴らしいところ。ここを改修するとともに、もっと居心地を良くするには絶好のタイミングだったのです。
堀:20周年の事業を考えたとき、斬新な展示スペースの増設などは物理的に難しかったため、それに代わるものとして、施設全体の美観に努めようと決めました。20年も経過すると建物の老朽化はかなり進みます。施設をしっかりと維持するための修繕コストは年々重くなっていました。中でも最も傷みの激しかったのがイルカショースタジアムでした。
他方で、我々はまた来たくなるような「居心地の良い水族館」をうたっています。20年という節目にそこを再認識したいと思いました。イルカショースタジアムはお客さまが滞在するスペースとして一番広い場所でもありましたし、本当に眺めも素晴らしいところ。ここを改修するとともに、もっと居心地を良くするには絶好のタイミングだったのです。

——日建設計に依頼した理由は何ですか?
堀:最初は日建設計ありきではなかったのです。でも、1年半ほど前に坂本さんと久しぶりにお会いする機会があり、安田さんともそこで初めて出会いまして、渋谷や代官山の沿線ブランディングをはじめとする都市再開発プロジェクトについて伺いました。
今、藤沢市も観光都市としての街づくりを進めていますが、まだまだ課題が山積み。そうした中で街づくりを手がけてらっしゃる2人のお話は大変興味深かったです。
また、リニューアルについても、単にイルカショースタジアムをきれいにしますだけだと、「木を見て森を見ず」のように、スタジアムの屋根はこういう風にしましょうとか、塗装はこれがいいですとか、細部の話ばかりになってしまう。そうではなくて、地域全体のグランドデザインを俯瞰した中で水族館がどうあるべきかを考えたかったのです。ですから日建設計の取り組みには期待が大きく膨らみました。
坂本:私自身、20年前の開業プロジェクトに携わりましたが、それからずっとお付き合いさせていただくような関係ではありませんでした。一方でその間に、私と安田は人々の言葉にならない思いを言語化し、街や施設の目指すべき方向性、つまりはコンセプトを作ったり、それを実現するデザインマネジメントを行ったりする仕事をしてきました。そういった経験を堀さんにお話ししたところ、今回のパートナーに選んでいただけたわけです。
堀:最初は日建設計ありきではなかったのです。でも、1年半ほど前に坂本さんと久しぶりにお会いする機会があり、安田さんともそこで初めて出会いまして、渋谷や代官山の沿線ブランディングをはじめとする都市再開発プロジェクトについて伺いました。
今、藤沢市も観光都市としての街づくりを進めていますが、まだまだ課題が山積み。そうした中で街づくりを手がけてらっしゃる2人のお話は大変興味深かったです。
また、リニューアルについても、単にイルカショースタジアムをきれいにしますだけだと、「木を見て森を見ず」のように、スタジアムの屋根はこういう風にしましょうとか、塗装はこれがいいですとか、細部の話ばかりになってしまう。そうではなくて、地域全体のグランドデザインを俯瞰した中で水族館がどうあるべきかを考えたかったのです。ですから日建設計の取り組みには期待が大きく膨らみました。
坂本:私自身、20年前の開業プロジェクトに携わりましたが、それからずっとお付き合いさせていただくような関係ではありませんでした。一方でその間に、私と安田は人々の言葉にならない思いを言語化し、街や施設の目指すべき方向性、つまりはコンセプトを作ったり、それを実現するデザインマネジメントを行ったりする仕事をしてきました。そういった経験を堀さんにお話ししたところ、今回のパートナーに選んでいただけたわけです。
頭の中のモヤモヤを言語化する
——今回のプロジェクトはどのようなアプローチで進めていったのでしょうか?
安田:最初に、どういう施設にしたいのかというコンセプトを作るのですが、それは我々がひねり出すのではなく、ワークショップに参加した水族館の皆さんの意見を基にします。
安田:最初に、どういう施設にしたいのかというコンセプトを作るのですが、それは我々がひねり出すのではなく、ワークショップに参加した水族館の皆さんの意見を基にします。

ワークショップでは、水族館をどうやってきれいにするとかではなく、例えば「1日中過ごしたくなる場所はどういうところですか?」「繰り返し訪れたくなる場所は?」といった根源的なニーズを引き出す問いかけをしました。
ただし、それを言葉で表すのはなかなか難しいため、施設の中で好きな場所、気になる場所などを自由に撮影してきてもらいました。大切なのは、誰が何を撮ったかというよりも、その対象物がどう切り取られているのかに気付くことです。こうした方法で皆さんが頭の中でモヤモヤと言葉にできなかったことを少しずつ言語化していきました。
次に、そのような場所に共通する概念を導き、それらを基に具体的なイメージを皆で一緒に考えていきました。
(分厚い冊子になった資料を堀さんに見せる)
ただし、それを言葉で表すのはなかなか難しいため、施設の中で好きな場所、気になる場所などを自由に撮影してきてもらいました。大切なのは、誰が何を撮ったかというよりも、その対象物がどう切り取られているのかに気付くことです。こうした方法で皆さんが頭の中でモヤモヤと言葉にできなかったことを少しずつ言語化していきました。
次に、そのような場所に共通する概念を導き、それらを基に具体的なイメージを皆で一緒に考えていきました。
(分厚い冊子になった資料を堀さんに見せる)

堀:これはすごいね!
安田:こちらは、ワークショップでコンセプトを検討する過程をまとめた資料です。我々は環境作りのプロですから、言語化するだけではなくて、その言葉を環境に落とし込むところまで取り組みます。言葉の整理と、環境の整備、(建物など)モノの整備を一気通貫で行いました。逆にそこまでやらないと「何だかイメージと違うな」というものが出てきてしまうからです。
堀:ワークショップにものすごく膨大な時間をかけていましたが、このプロセスが最も重要なポイントだったと改めて実感しますね。
坂本:わりとスケジュールはタイトで、お声掛けいただいたのが2023年夏。そこから年内には何をどう作るかを決めて、工事に入らなくてはなりませんでした。今回は一から施設を作り上げるわけではないですが、それでも時間は限られているため、手戻りなく進める必要がありました。考え方や目指しているものが途中で「違う」とならないように、出来たときに皆さんに納得いただけるような合意形成を進めていきました。
堀:建物も生き物だと思っています。設計事務所との関係は建物が引き渡されたらそれで終わりというケースも多いとは思いますが、元々この水族館は日建設計の設計だし、当時の坂本さんたちが持っていた最高の感性が発揮されたもの。だからリニューアルするならば、違うデザイナーに頼むよりも、この20年で多くの経験を積まれた坂本さん自身にお願いしたほうが、過去から未来へのつながりもできるし、一番よいものができるはずだと確信しました。
ちょっと先走ってしまうと、10年後も楽しみにしているのですよ。日建設計がどのように進化させて、“新・新江ノ島水族館”を生み出してくれるのか、すぐにワークショップを開いてもらいたいくらいです(笑)。
安田:さっそく今から始めないと間に合いませんね。
安田:こちらは、ワークショップでコンセプトを検討する過程をまとめた資料です。我々は環境作りのプロですから、言語化するだけではなくて、その言葉を環境に落とし込むところまで取り組みます。言葉の整理と、環境の整備、(建物など)モノの整備を一気通貫で行いました。逆にそこまでやらないと「何だかイメージと違うな」というものが出てきてしまうからです。
堀:ワークショップにものすごく膨大な時間をかけていましたが、このプロセスが最も重要なポイントだったと改めて実感しますね。
坂本:わりとスケジュールはタイトで、お声掛けいただいたのが2023年夏。そこから年内には何をどう作るかを決めて、工事に入らなくてはなりませんでした。今回は一から施設を作り上げるわけではないですが、それでも時間は限られているため、手戻りなく進める必要がありました。考え方や目指しているものが途中で「違う」とならないように、出来たときに皆さんに納得いただけるような合意形成を進めていきました。
堀:建物も生き物だと思っています。設計事務所との関係は建物が引き渡されたらそれで終わりというケースも多いとは思いますが、元々この水族館は日建設計の設計だし、当時の坂本さんたちが持っていた最高の感性が発揮されたもの。だからリニューアルするならば、違うデザイナーに頼むよりも、この20年で多くの経験を積まれた坂本さん自身にお願いしたほうが、過去から未来へのつながりもできるし、一番よいものができるはずだと確信しました。
ちょっと先走ってしまうと、10年後も楽しみにしているのですよ。日建設計がどのように進化させて、“新・新江ノ島水族館”を生み出してくれるのか、すぐにワークショップを開いてもらいたいくらいです(笑)。
安田:さっそく今から始めないと間に合いませんね。
湘南の景観を存分に感じてもらえる設計
——設計において重視した点や工夫した点はありますか?
坂本:イルカショースタジアムという場所は、この地域の中でどういう位置付けだろうかという少し引いた視点を持ちました。
20年前の設計思想は、イルカを鑑賞する客席をベストなものにすることでした。ただし、もっといろいろな使われ方があってもいいのではないかというのが、ワークショップからも見えてきました。せっかく素晴らしいロケーションなのだから、イルカショーをやってない時間帯もゆっくり過ごしてもらいたい。そういった環境にするためには、まさに居心地の良い場所に対する考え方を、20年前のそれとは変えなくてはならない。そこが今回一番こだわった部分です。
長く滞在してもらうには、当然椅子の座り心地も大切ですし、美味しいものを食べたり、飲んだりもしたくなる。そうすると料飲施設も今まで以上に施設と一体感を持って豊かな商品が提供できた方が良いわけです。
坂本:イルカショースタジアムという場所は、この地域の中でどういう位置付けだろうかという少し引いた視点を持ちました。
20年前の設計思想は、イルカを鑑賞する客席をベストなものにすることでした。ただし、もっといろいろな使われ方があってもいいのではないかというのが、ワークショップからも見えてきました。せっかく素晴らしいロケーションなのだから、イルカショーをやってない時間帯もゆっくり過ごしてもらいたい。そういった環境にするためには、まさに居心地の良い場所に対する考え方を、20年前のそれとは変えなくてはならない。そこが今回一番こだわった部分です。
長く滞在してもらうには、当然椅子の座り心地も大切ですし、美味しいものを食べたり、飲んだりもしたくなる。そうすると料飲施設も今まで以上に施設と一体感を持って豊かな商品が提供できた方が良いわけです。

あとは、座席ではない場所にも少し手を加えました。客席最後尾の落下防止用の手すりにカウンターを付けたのです。すると、皆さんはショーをやっていない時間帯でもそこに立ち止まって飲み物を置くなどするようになりました。滞在時間を少しでも長くできるような環境に変えるためのデザインはいろいろと提案しましたね。

——実際、お客さんの反応はいかがでしたか?
堀:イルカショーがなくてもあの場所を利用している人はいます。座り心地もすごく良いですし、休憩している方はすごく増えたと思いますよ。併設する飲食店もリニューアルし、おかげさまで売り上げは倍増しました。
スタジアムからの景観は本当に素晴らしく、富士山も江の島も烏帽子岩も一望できます。「こんなに江の島が近いならちょっと足を伸ばしてみようか」と、地域の回遊性を高めることにも一役買っています。湘南エリアを感じていただける場所として強くお勧めできるようになりました。
堀:イルカショーがなくてもあの場所を利用している人はいます。座り心地もすごく良いですし、休憩している方はすごく増えたと思いますよ。併設する飲食店もリニューアルし、おかげさまで売り上げは倍増しました。
スタジアムからの景観は本当に素晴らしく、富士山も江の島も烏帽子岩も一望できます。「こんなに江の島が近いならちょっと足を伸ばしてみようか」と、地域の回遊性を高めることにも一役買っています。湘南エリアを感じていただける場所として強くお勧めできるようになりました。

坂本:景観の魅力を高める上で細かい調整をしました。例えば、屋根の存在感はあった方がいいのか、消えた方がいいのか、消えるとすればどれくらいなのか、など。選択によって景色の感じ方もまるで変わってしまいます。まさに堀さんのお母さまに教わったことを思い出しながら、この環境に身を置いていることの豊かさを感じるには、どのような色使いにすればいいだろうと、かなり時間をかけて議論しました。

今後も広がる水族館の価値
——堀さん自身は地域におけるこの水族館の意味合いや存在意義について、どうお考えでしょうか?
堀:神奈川県や藤沢市がそれぞれ観光立県、観光立市を標榜する中で、湘南・江の島エリアは重点地域に位置づけられています。ですから、この水族館で湘南を感じてもらうことによって、それが神奈川県や藤沢市の観光評価につながるよう取り組むのは会社の使命だと考えています。
そのためには地域連携も重要です。例えば、江ノ島電鉄や小田急電鉄、あるいは行政の観光課など、官民が一体となってもっと湘南・江の島エリアのコンテンツを楽しませる施策を進めていく。その結果、地域全体の観光客数を増やしていきたいです。既にそれを目指したコンソーシアムも立ち上げています。
湘南・江の島エリアを含む藤沢市の観光客数は2023年に1960万人となりました。我々は常にこの数字との相対性を見ています。観光客の1割が水族館に立ち寄ってくれる関係性ができれば、1960万人で196万人。2000万人では200万人。だから地域全体の母数を上げていくのも当社として大切です。渉外営業部隊は積極的に地域と連携して、もっと藤沢市に人が来てもらえるよう、皆さんと一緒になって汗をかいています。
——日建設計はこれまでも街のコンセプト作りやデザインマネジメントに取り組んできました。そうした立場から改めて「地域」や「場所」をどのように捉えていますか。
安田:先ほど堀さんから回遊性の話が出ました。回遊性とは何かについて、私たちはよく議論をしてきました。「今日はこの街を回遊するぞ!」という人は多分そういないと思います。でも、目的地から目的地へと移動することはあり得る。つまり、目的がつながっていることが重要なのです。さらに例えば、歴史や文化的なものの観光、買い物、飲食など、3つくらいの目的があれば、その街には何度でも行きたくなる。いろいろな人がそうした行動をとっていると、結果として回遊っぽく見えるわけです。
さまざまな議論の中で、もう一つキーワードとして出てきたのが「多義性」。私にとっての水族館と、坂本が思っている水族館は認識が違うわけですよ。だから、イルカショースタジアムに関しても、イルカを見る場所ではないという考え方があってもいいはずです。そういう人がいれば、この場所が持つ意味合いは2つになります。それが3つ、4つになることで、ここに訪れる目的もその分増えていきます。もしかしたら水族館はこれまでとはまったく違う価値を提供できる可能性があるのではと思いますし、そこについてもぜひ一緒に取り組んでいけたら嬉しいですね。
堀:確かに、日本語では「水族館」ですが、語源はラテン語の「アクアリウム(aquarium)」。アクアは水、リウムは場所。そう捉えると、新江ノ島水族館の多様性はまだまだ広がりますし、お客さまとのコミュニケーションの場所としてどう活用していくかをもっと考えていきたいです。
イルカショースタジアムのリニューアルは20周年の節目として一旦は完成しました。でも、施設や場所もまた生き物ですから、これを今後も進化させていかなければなりません。そのためにも我々と日建設計、お互いの関係性が継続し、共に歩んでいけることはとても楽しみです。
——本日はありがとうございました。
堀:神奈川県や藤沢市がそれぞれ観光立県、観光立市を標榜する中で、湘南・江の島エリアは重点地域に位置づけられています。ですから、この水族館で湘南を感じてもらうことによって、それが神奈川県や藤沢市の観光評価につながるよう取り組むのは会社の使命だと考えています。
そのためには地域連携も重要です。例えば、江ノ島電鉄や小田急電鉄、あるいは行政の観光課など、官民が一体となってもっと湘南・江の島エリアのコンテンツを楽しませる施策を進めていく。その結果、地域全体の観光客数を増やしていきたいです。既にそれを目指したコンソーシアムも立ち上げています。
湘南・江の島エリアを含む藤沢市の観光客数は2023年に1960万人となりました。我々は常にこの数字との相対性を見ています。観光客の1割が水族館に立ち寄ってくれる関係性ができれば、1960万人で196万人。2000万人では200万人。だから地域全体の母数を上げていくのも当社として大切です。渉外営業部隊は積極的に地域と連携して、もっと藤沢市に人が来てもらえるよう、皆さんと一緒になって汗をかいています。
——日建設計はこれまでも街のコンセプト作りやデザインマネジメントに取り組んできました。そうした立場から改めて「地域」や「場所」をどのように捉えていますか。
安田:先ほど堀さんから回遊性の話が出ました。回遊性とは何かについて、私たちはよく議論をしてきました。「今日はこの街を回遊するぞ!」という人は多分そういないと思います。でも、目的地から目的地へと移動することはあり得る。つまり、目的がつながっていることが重要なのです。さらに例えば、歴史や文化的なものの観光、買い物、飲食など、3つくらいの目的があれば、その街には何度でも行きたくなる。いろいろな人がそうした行動をとっていると、結果として回遊っぽく見えるわけです。
さまざまな議論の中で、もう一つキーワードとして出てきたのが「多義性」。私にとっての水族館と、坂本が思っている水族館は認識が違うわけですよ。だから、イルカショースタジアムに関しても、イルカを見る場所ではないという考え方があってもいいはずです。そういう人がいれば、この場所が持つ意味合いは2つになります。それが3つ、4つになることで、ここに訪れる目的もその分増えていきます。もしかしたら水族館はこれまでとはまったく違う価値を提供できる可能性があるのではと思いますし、そこについてもぜひ一緒に取り組んでいけたら嬉しいですね。
堀:確かに、日本語では「水族館」ですが、語源はラテン語の「アクアリウム(aquarium)」。アクアは水、リウムは場所。そう捉えると、新江ノ島水族館の多様性はまだまだ広がりますし、お客さまとのコミュニケーションの場所としてどう活用していくかをもっと考えていきたいです。
イルカショースタジアムのリニューアルは20周年の節目として一旦は完成しました。でも、施設や場所もまた生き物ですから、これを今後も進化させていかなければなりません。そのためにも我々と日建設計、お互いの関係性が継続し、共に歩んでいけることはとても楽しみです。
——本日はありがとうございました。


