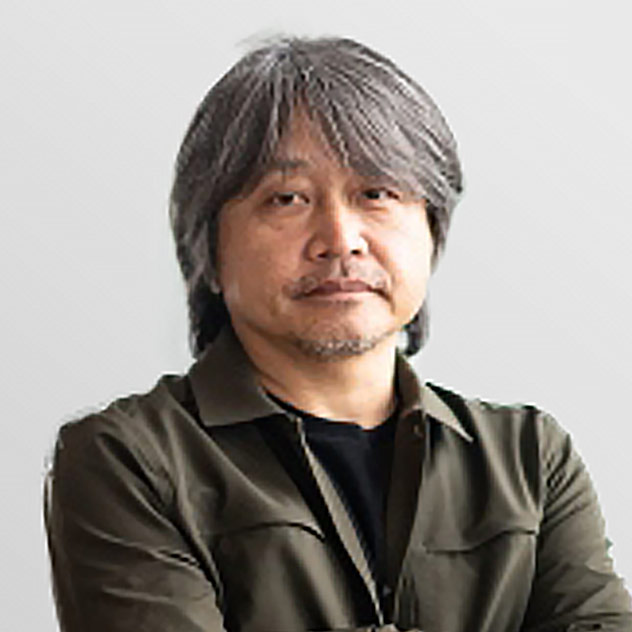デザイナー座談会2
デザインに投資すると、どんな「付加価値」が生まれる?
Scroll Down
2024年4月1日付の日建スペースデザイン(以降、NSD)と日建設計の合併に伴い、設計監理部門にスペースデザイングループ(以降、SpDG)を発足いたしました。そこで、インテリアデザイン業界で数多くの現場を見守り続けてきた月刊商店建築の塩田健一編集長と、これから SpDG と空間創出するクライアントやパートナーに共有したい3つのテーマを設定し、インテリアデザインの未来を語る座談会を開催しました。
第1回 社会から「インテリアデザイナー」が消えてゆく?
モデレーター 株式会社エイトブランディングデザイン代表 ブランディングデザイナー 西澤明洋氏
第2回 デザインに投資すると、どんな「付加価値」が生まれる?
モデレーター 月刊商店建築 編集長 塩田健一氏 (今ココ)
第3回 デザイナーが「アート」描いちゃいました⁈
モデレーター ジャーナリスト 山田泰巨氏
今回は第2回として、月刊商店建築の塩田編集長をモデレーターにお迎えし、デザインの効果を最大限に発揮させるため、その意義と必要性をクライアントに伝えて実現に導いてきた、取り組みの「リアル」を語りました。
【参加者】
日建設計 設計監理部門 スペースデザイングループ
戸井 賢一郎
遠山 義雅
伊藤 愛
王 笛
【モデレーター】
月刊「商店建築」編集長
塩田健一氏

遠山義雅(以下、遠山) たとえば私が担当した東京都中央区の「BNI(バンクネガラインドネシア)東京支店」(2021年竣工)。これは、インドネシアの国営銀行の日本支店で、銀行の機能を超えて、インドネシアの文化を訴求する「都市に開かれた銀行」を目指しました。
 BNI(バンクネガラインドネシア)東京支店
BNI(バンクネガラインドネシア)東京支店
写真:益永研司写真事務所
 遠山 義雅
遠山 義雅
塩田 そうしたコンセプトワークにはどのくらい時間をかけたのですか?
遠山 この案件ではスケジュールがタイトでしたので、あまり時間はかけられませんでした。その分、コンセプトを徹底させることを心がけました。
時間があればいいデザインになるとも限らないんですよね。期間が長いとブレていくこともありますし。タイトなスケジュールの場合、クライアント様も含め、案件に関わるみなさんも始めのコンセプトを忘れないでいられるので、最後まで純度の高いままコンセプトを貫けることが多いかもしれません。「短距離走」、嫌いではないです(笑)。
建物や敷地のポテンシャルを再評価してリブランド
 伊藤 愛
伊藤 愛
 コンセプト提案 🄫Nikken Sekkei Ltd
コンセプト提案 🄫Nikken Sekkei Ltd
 nol hakone myojindai イタリアンレストラン cresita
nol hakone myojindai イタリアンレストラン cresita
写真提供:東急不動産
伊藤 「Naturally(自分らしく、自然体で)」「Ordinarily(普段通り、暮らすように過ごし)」「Locally(その土地の日常に触れる)」をブランドコンセプトに持つ「nol」というホテルブランドがありまして、タイミングとしてはクライアントのほうで2号店目を検討している状況でした。京都で1号店(2020年開業)のローンチ後、今回は箱根という立地で2号店をどのようにプランニングするか、既存の建物と環境を最大限に生かしてホテルをどのようにリブランドするかということが私たちのテーマとなりました。
キーワードは「晴耕雨浴」。天気のいい日は敷地内の畑で汗を流し、雨が降ったら温泉でくつろぐ。滞在を通して、豊かな環境の中で自分を取り戻す。そんな体験ができる場にするという体験を軸とした提案をホテルのデザインに落とし込んでいきました。
塩田 設計依頼を待つのではなく、こちらから発信して、種をまいていったんですね。
遠山 この案件は、もとのホテルの価値を上書きして、新しいコンセプトに乗せながら、新たな価値を付加していく、という形ですよね。こうした改修では、私たちデザイナーが参加することで、もともとの建物や敷地に存在していたポテンシャルを再評価して、新たな側面を見せることができます。私たちの仕事の価値がよくわかっていただけるのでは。
伊藤 新築では基本的に当初の計画通りに進行するのが前提になりますが、改修の場合、図面と違う箇所があるなど、予想しない問題がしばしば起こります。そのたびにコンセプトに立ち戻って柔軟に対応していきます。そういう意味では、着工前のコンセプトワークが重要になりますし、私たちがその段階から関わる意義があると感じています。
コンセプトワークの段階からデザイナーが参加する意義
王笛(以降、王) 2024年7月に開業した「THE OSAKA STATION HOTEL, Autograph Collection」では、日建設計は客室のインテリアを担当しました。
初代大阪駅の地に誕生するので、ホテルブランドコンセプト「THE OSAKA TIME」を受け、デザインフィロソフィーには、「TIME TRAVEL(時空の旅)」として構築され、館内各エリアを巡ることで大阪の歴史や文化、駅や鉄道の記憶を表すモチーフ、工芸や素材をちりばめていきました。
複数のデザイン会社が入っていたプロジェクトでしたが、コンセプトストーリーを共有できていたので、統一感のある世界観でデザインをアウトプットしていくことができました。
 王 笛
王 笛
王 すべての空間にストーリーを徹底的に組み入れようということで、みんなで大阪駅や鉄道に関する資料をかなり読み込んで、アイディアを出していきました。
塩田 同時期に建った他のホテルとも明らかに質の違うものになったと思います。
王 ありがとうございます。そのほか、大阪・中之島の「未来医療国際拠点 Nakanoshima Qross(中之島クロス)」内で計画した「ハイメディック大阪中之島コース」のデザインもオリジナリティのあるものになったと思います。
ビル自体、先進的な医療施設と研究機関が入居する建物で、「ハイメディック大阪中之島コース」もエグゼクティブを対象とした会員制の人間ドック・検診サービスを提供する施設となっています。中之島という立地から、水の都の生命力、癒やしなどを感じていただけるように、照明と色彩とアートで水のイメージを表現しました。
 ハイメディック大阪中之島コース
ハイメディック大阪中之島コース
写真:DAISUKE SHIMA (adhoc)
王 クライアント様とは他地域の同施設を踏まえて、「最先端医療を取り扱う施設として先進性を強調して」「地域性をもっとアピールして」「見たことのない空間を」といった具合に、ご要望をお聞きしながら、コンセプトワークからまとめていきました。病院らしい空間というよりはラグジュアリーな体験を得られる場に、という着地点を見つけることができてよかったです。
デザインに遊び心を出すときは徹底的に
戸井賢一郎(以降、戸井) 2023年10月に開業した「ホテルメトロポリタン 羽田」も、コンセプトを徹底的に反映することができた案件でした。
羽田空港跡地第1ゾーン整備事業として開発が進む、“HANEDA INNOVATION CITY”(HICity)ZONE Aの5階~10階に計画されたホテルで、すぐ隣が羽田空港ということで、その立地をどう生かしてデザインに取り込んでいくかがポイントとなりました。
 戸井 賢一郎
戸井 賢一郎
全14種類の客室は、全体的に落ち着いた色合いの「BARライク」なインテリアを基調として、羽田空港を一望できるエアポートサイドの客室や、開放的な景色が楽しめるリバーサイドの客室なども用意しています。
客室内では近未来的な空港の照明とは対照的に、ガラスグローブの大きな照明機器をアイキャッチにして、柔らかなフィラメント電球のレトロな雰囲気の灯りで心地よさを演出しました。窓際には窓の外に広がる空港の景色をゆっくりと楽しめる「BAR」をイメージしたハイカウンターを設けています。
 ホテルメトロポリタン 羽田
ホテルメトロポリタン 羽田
写真:益永研司写真事務所
戸井 おかげさまで、海外からのお客様がSNSにアップしてくださるなど、ゲストの新しい体験をベースに評判が広がっています。デザインでホテルのブランディングに貢献できた事例です。
解釈の余白と、デザインの価値とは
伊藤 戸井さんはコンセプトを徹底させているので、レストランや客室、共用部と先方の担当者が異なっていても、全員にイメージが浸透するんですよね。同じチームで仕事をしていると、戸井さんのデザインフィロソフィーが自然に伝わってくる。その情熱が温度感を損なわずにクライアント様を動かし、施工者のみなさんも巻き込んでいく。そういういいスパイラルが生まれているように感じます。
王 デザインって、一見するとただの飾りだし、余分に思われがち。でも、クライアント様に意図や思いが伝わっていると、価値や意味を認めていただけることが多いようです。
戸井 でも自分たちがやりたいから、だけでは通じない。このデザインを採用することで、案件全体にメリットがもたらされて、実際にその建物を利用する方々にも利益がもたらされるようでないと提案する意味がないと思っています。
塩田 そこで生まれる空間体験が豊かになることが必要ですよね。そのためにはどんな要素が必要だと思いますか?
遠山 言語化することは非常に重要だと思います。
伊藤 「nol hakone myojindai」では、「晴耕雨浴」という言葉が生まれた瞬間、一気に物事が動き始めました。
塩田 全体のデザインでも部分的なディスプレイであっても、目的や理由を提示することはとても重要。企業としての活動や、消費者の購買意欲なども、目的や理由が大きく左右する。そこに、緻密でしっかりと練り上げられたストーリーやコンセプトが求められています。
遠山 プランをストーリーに落とし込んで語る際には、多面的な視野を持つことを意識しています。デザインする側だけでなく、運用する側、利用する側、それぞれの視点からはどうとらえられるか。自問自答していくと、デザインの幅が広がるように思います。
塩田 デザインってすべてがきっちり言語化できない部分もありますよね。
伊藤 説明不能な部分は確かにあります(笑)。そういう部分は、基本的なコンセプトからズレていなければ、現場レベルで違う解釈が生まれていても面白い。
遠山 解釈の余地があるということは、他者にとっては参加する余地があるということ。解釈の余地がないと、竣工後にもその空間に多様なシーンが生まれにくい。それってさびしいことだと思うので、提案するとき、あまり作り込みすぎないということも意識しています。
塩田 みなさん個性豊かですよね(笑)。デザインもプレゼンもコンセプトも、とても明快だから、伝わりやすい。やりすぎくらいの尖ったデザインだけど、他を寄せ付けないものではなく、誰もが自分ごととして思いを寄せられるような余白がちゃんとある。
もしかしたら合理的には正解なプランというものが存在しているとしたら、みなさんのデザインはそこには含まれない要素なのかもしれない。でもそれではつまらないものになるから、みなさんのお仕事の価値があるんですよね。
引き出しがたくさんある。デザイナーの個性を組み合わせてフォーメーションも組める。それが、日建設計 スペースデザイングループの強みなのかもしれません。
施主となる方々が思い描く事業イメージが、こうした各デザイナーの個性と結びつく。そして、デザイナーに「お任せ」ではなく、施主とデザイナーが二人三脚で「突き抜けたデザイン」を追い求めてみる。その結果として、そこでしか体験できない空間が生まれ、集客や収益に結びついていく。そんな一度きりの奇跡的な出会いによる空間を、今日の座談会でたくさん見せていただいた気がします。そして、私としても、日々の取材を通して、そうした空間に出会えることこそが、最大の醍醐味だと感じています。これからも日建設計の皆さんのプロジェクトを楽しみにしています。

塩田 健一(しおた けんいち)月刊商店建築 編集長
2006年より「月刊商店建築」編集部に所属。カフェ特集など毎月の店舗取材を担当する他、「コンパクト&コンフォートホテル設計論」「CREATIVE HOTEL & COMMUNICATION SPACE」など ホテルに関する増刊号も制作。2017年2月より現職。